[ぼらぷらSDGs小論文]
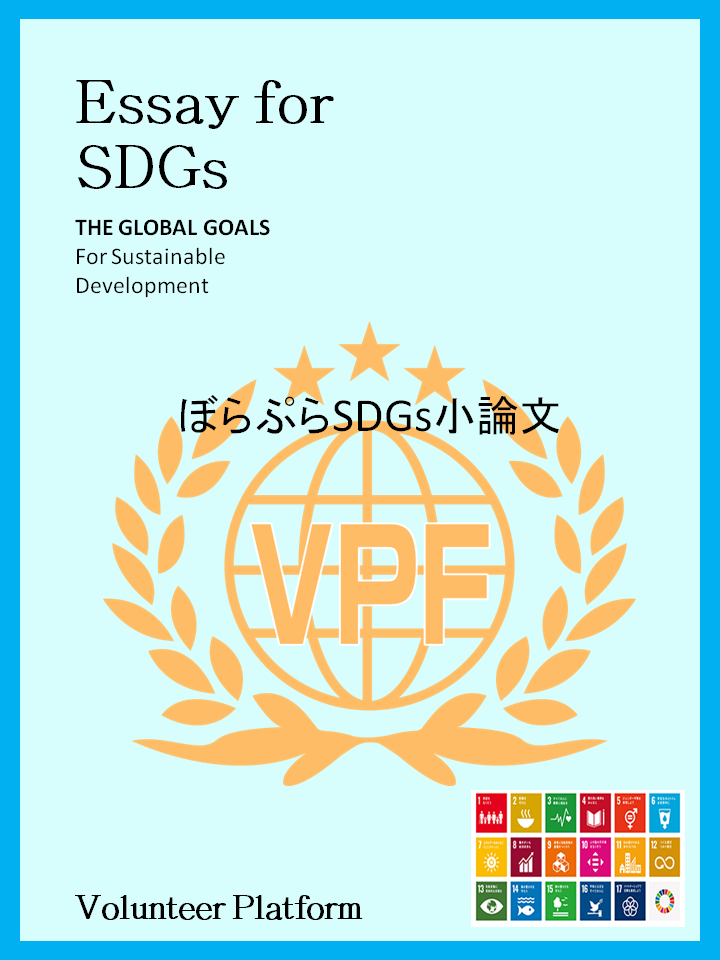
『SDGsと食料問題』
小論文
『SDGsと食料問題』
今回の学習から取り上げたテーマとして、日本や世界の食料問題がある。それに対して自分は何ができるかを考える。まず日本の食糧事情について、今後後継者不足などの理由により不足していくが、だからこそ自給率を上げる必要があると考える。また日本は以前から食料を外国の輸入に頼っている割合が高い。それにより自給率が非常に低いことが指摘されている。具体的に日本の食糧自給率としては、生産額ベースだと58%、カロリーベースだと38%となっている。特に小麦は12%、牛肉36%、豚肉48%、エビ3%、バナナ0%など、ほぼ輸入しないと得られない食料もあり、その数字からも深刻な状況であることがわかる。もちろん国内の気候状況で育てることができないものがあるのはやむを得ないが、需要に沿って自給率を上げる必要があると考える。(研修資料第6回を参考)
日本国内の自給率を上げるためには何をすべきか。それは労働力を補うことだ。状況として今後の人口減少の問題もあり、今までの団塊の世代の頃のやり方は通用しなくなると考える。農業労働者が高齢になるにつれて後継者不足など人手不足は深刻になり、今まで通り仕事ができなくなることは予想できる。農業とは異なるが人手不足の例として、今年問題視されていた物流業界の問題があげれられる。物流業界の人手不足の深刻さによって配送が遅れる、運行していたバスの本数が減るなどの事例をニュースで見た人もいるだろう。これからはさらに農業界にも同じように影響し、作物を育てられなくなるなど深刻な食糧難の状況を引き起こすと考えられる。そこですべきことは、労力を補う必要性があるということだ。それがIT技術の活用だと考える。最近はIoTやAI技術の進化が著しく、この技術を使い人に変わって業務を行うこともできるため将来性が期待できる。
しかし少し前まではAIが人の仕事を奪うと言われて恐れられていた。今ある仕事が将来半分くらいになると予測した記事を読んだことがある。今では少しずつだが世間に受け入れられて労働力を補うことができてきていると考える。もちろんAIはまだ未開発なところもあり、どこまで人の代わりになるのか不明なことが多いが、今後はAI技術に頼り人が操作をしていく必要があると考える。農業では作物の収穫時期の予測や生育、ドローンを使った農薬散布などの事例がある。このAI技術を用いて、今まで作り上げてきた技術をさらに発展させ、効率的に食料を生産できるシステム作りをする必要があると考える。
ここまでで日本の食糧事情をざっくりと見てきたが、大きな流れから自分ができることとして、まずはIT技術の取得と野菜などの食物の栽培から始めることだと考える。IT技術は今後必ず必要となるので、常に最新の情報を追わないといけないが、活用できると便利なのでスキルを身につけたい。また野菜の栽培は既に自宅の鉢でトマトを栽培しているが、まずは小規模栽培で試し成功したら規模を広げて作物を栽培し、自給自足につなげていきたい。まずは自宅でそして日本で、そして世界のSDGsにつながっていくと考える。
オンライン研修を受講した感想
総合的な満足度
満足
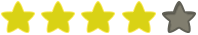
受講前の気持ち
コロナ下でもできるボランティア活動を探していた、SDGsについて学びたい
受講後の気持ち
一生モノの学びになった!
視野が広がった!
SDGsを自分ゴトとして捉えられるようになった!
研修を受講した理由を教えて下さい
オンラインのボランティアをやってみたかったので受講を申し込みました。また自分の就業のためや現地のボランティア活動が難しいが、オンラインであれば自宅でも参加ができると考えたからです。他にSDGsについて詳しく学び、実生活に役立てたいと考えていました。
研修を受講した感想は?
オンライン研修という形で参加しましたが、思いの外SDGsについて詳しく学ぶことができたと思います。一つ一つの事例を学び、学びを自分の生活や経験に落とし込み、SDGsを意識して取り組むことができそうです。LIVEアクティビティは子供達や先生と一緒に参加し、日本語を教えたりカンボジアの文化を共有したりとても楽しい時間を過ごすことができました。以前からやりたかった国際協力活動をオンラインで参加できたことは、とても嬉しかったです。
今後、今回の経験をどのように活かしていきたいですか?
今後は小論文で書いた食糧問題について、小規模で野菜を育てるところから実施して行こうと考えます。将来的には自給自足できるようになるのが目標です。
これから受講される方へアドバイスお願いします!
SDGsは大人でも学んだほうが良いです。ぜひ関心を持って持続可能性に貢献しましょう。
ぼらぷらへ応援メッセージ
会員様から頂いたメッセージは私達にとって何よりの励みになります!!
カンボジアでのアクティビティはとても楽しく参加させていただきました。参加してくださった先生と子供達に感謝です。また毎週研修の応援メールをお送りいただきありがとうございました!受講目安があると学習がはかどりました。お陰様で無理なく学習を続けることができました。
最後に、この学習を進めている途中で次の仕事も決まりました。
本当にありがとうございました!






 LINE相談
LINE相談
